|
- 13 -
船田―先生のお話の中で、いろいろな細かい規制の積み重ねのお話がありましたが、話を少し戻しますと、教育でも大いにいえることです。大きくいえば、学習指導要領がありそれに基づいた教科書があります。教科書はある意味では、インターネットとは対極にあるもので、知識を体系的に並べてあるだけです。子供達の中に教科書を読んで興味のわく子はほとんどいません。インターネット教育の実例を見ますと、子供達が非常に自由に発想し、彼らの興味に重点を置いています。そしてたとえ彼らの興味が教科書とはずれても、その興味をそがないように「なぜ、このようなことが起こるのか、もう一度インターネットで調べてごらん」というように、どんどん子どもたちの興味に合わせて自由に授業展開が出来るのです。
もちろん、基礎基本というのをある程度教えなければならないのはわかりますが、がんじがらめの状況の中では本当の情報教育が出来ないのではと思っています。授業時間が50分とか45分に区切られています。学校で使われているインターネットの回線はすごく細いため、つながるまでに時間がかかるのです。したがって、途中で授業が終わってしまう。そのまま1日2日たてば、子どもたちの興味は他へいってしまう。もっと緩和していかなければ、日本のIT革命のスピードはすごくゆるいものであろうと思います。
つい三日前まで、勉強のためにアメリカへ行ってまいりました。情報革命の次、つまり「ポストIT革命」として「生命情報科学」―バイオインフォマティクス―がアメリカで注目されています。生体の中にある遺伝子やヒトゲノムが解明されたのです。アメリカは遺伝子の情報をたくさん持ったわけです。それで個人個人の現在から将来に起こりうる疫病が、遺伝子の状態を調べることによってほぼ完璧に予想できるというのです。
そしてアメリカの強みというのは、常に最先端を走っていること。またそれに携わる頭脳の育成や戦略的かつ効果的な研究費の使い方が合理的で、その成果もすぐにビジネスに直結させる。ベンチャービジネスに力を入れ、彼らが動きやすいように様々な規制を緩和しているというような、アメリカのダイナミズムを肌で感じてきました。先生のお話にあった、小さな規制の積み重ねが日本にとって大きなマイナスになっているというご指摘、これの全く裏返しのことが、アメリカで行われていました。先生もアメリカにおられたということで、最近のアメリカの動きについてはどうお考えでしょうか?
竹中―お話をうかがってさすが船田先生だと思いました。このヒトゲノムの解明というのは、われわれ人類にとってものすごく大きなイベントであるとの位置付けで、IT革命との関連でやらなければなりません。大げさな話で恐縮ですが、先ほど産業革命の例を出しました。産業革命の本質はなにかと言うと、専門家から言うとこうなります。産業革命で機関車ができました。自動車や飛行機が出来て、機械文明が産業革命から始まります。
実はこれをさかのぼる中世の時代に、天才レオナルド・ダ・ヴィンチは車の絵、飛行機の絵、みんな描いているのです。しかし天才の彼も見抜けなかったものが一つある。動力です。
彼の絵に出てくる飛行機は風に乗っている、鳥に引っ張ってもらう。つまり自然の動力しか出てこないのです。だから夢は夢のままで終わっていたのですが、そこにワットの蒸気機関車が出てきました。産業革命の本質は動力革命だったのです。
デジタルな技術。これが動力に相当するものだと思います。だからIT革命という言い方は必ずしも正しいとは思いません。デジタル革命というべきなんです。デジタル革命の一番分かりやすい例としてITが出てきました。デジタルというのは先ほど言ったように数字です。音楽も映像も数字に直すから早く送れる。数字に直しておくから、復元する時にものすごく正確にいい音で聞けるんです。
実はデジタルの技術を使ったから、ヒトゲノムの解読が可能になったんです。遺伝子文字が30億あるとする。遺伝子文字と我々が使う文字を一緒には出来ませんが、もし我々の文字で30億を換算すると、朝刊夕刊合わせて新聞紙50年分なのです。デジタルで数字に直してそれを高速解読するから読めるわけです。
今度は薬に劇的な影響が現れてくるはずです。われわれの遺伝子情報が解読されて、個人の疫病にあった、まさにオーダーメイドの薬が出来るわけです。同時に新しい物質がどんどん発明されていって、もう情報革命ではなく完全な物質革命の様相を呈してくるわけです。
ある専門家の指摘ですが、今までアナログ技術の中で500年間の間にわれわれが見つけた薬は400種類しかないそうです。これはさながら海の水をバケツで掬いつづけることと同じで、500年間掬いつづけたら、たまたま400種類見つけましたというものです。デジタルな技術で海の水を1センチ刻みで全部見ていったら、今後10年間で2000種類の薬が出てくるという議論がされています。
そこでアメリカはなにをやったかというと、今後10年が勝負だと割りきったわけです。世界中の科学者を全部連れてこいと、移民法を改正しました。アメリカがそこまでやったものだから、トルコ人の移民で懲りたはずのドイツまでもが改正し始めた。日本は発想において数段遅れていると思います。
あのヒトゲノムの解読を刺激したのが、セレーラ・ジェノミックス社。そこにベンター博士がいました。ナショナルチームにベンターのライバルになるコリンズ教授がいました。ベンター対コリンズの争いだったわけです。コリンズはノースカロライナ州立大学出身。ベンターはカリフォルニア州立大学サンディエゴ校の出身。もちろんいい大学ではありますが言いたいのは、ハーバード、プリントン、スタンフォードではないということ。それだけ本当に実力のあるところにお金をつけて、資源の最大活用をやっている。人間の能力を最大限に発揮できる教育、社会を作っていかなければならないと思います。
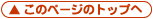
|