|
- 12 -
船田―ありがとうございます。私も学校教育における情報教育を進めようとやっておりました。選挙前のことですが、自民党の中に「情報教育に関する委員会」を作りました。日本では、コンピュータの部屋を各学校で必ず一つ作り、コンピュータを整備していますが、実際に子供達がパソコンを動かす、インターネットにつなぐという情報教育がまだまだできていないというのが実感でした。ハード面ではお金をかけさえすればいいのですが、どうつなげて、どう利用していくかというソフトの面が、日本の場合非常に遅れている。へたをするとそこは「開かずの教室」になってしまっているようです。
今では普通の小学校も情報リテラシーのある先生が1人や2人は出てきましたから、コンピュータ関連の話が持ち込まれてくると、彼らに任せて他の先生は全く触れない。やはり学校教育における情報教育がまだまだ不十分であると提言したのですが。
竹中―先生がご指摘されたのはとても重要な問題でかつ悩ましいものです。例えば「開かずの教室」になってしまったとしても、学校はなにも困らないのです。教育の中には競争というメカニズムが働かないから誰も淘汰されるメカニズムがない。もう一つ重要なことは教えられる人が全くいないのです。慶応大学の大学院生がボランティアでやったことですが、彼らが教えたら子供はものすごく伸びるんです。大学生や大学院生のような最先端のことをやっている人が、子供に対してフレンドリーに教えれば、成果は上がるに決まっているんです。でも教員免許をもっていないから教えられない。気が付いてみるとそういった小さな犠牲の積み重ねが、トータルとしての効果の発揮を阻害していると思います。
ITの問題を考える時、この小さな犠牲の積み重ねというのがキーワードになると思います。中央区に進出していたアメリカの会社が新宿区に引っ越すんです。そばに流れる川の下にケーブルを通させてくれないからです。河川法があって、やるのに半年かかるそうです。こういうことの積み重ねが事態を全く動かさなくしてみる、だからここでIT戦略が、もう一つ提案していることは、この際「特区」を作ってみることです。小さな規制を全部なくすことは出来ませんので、例えば、ある地域を「特区」に指定してみるわけです。これは、要するに中国が市場経済戦略として深に特区を作ったことと同じです。社会主義をいきなり変えることは出来ませんので、特区に使用という事と同じで、特区方式をやるべきだと思います。なぜ三重県なのかというと、それはどこでもあげられるものではなく、地引網等の関係で必ず漁業保証の問題と絡んできてあげられないのです。ところが、英虞湾はあげられたのです。真珠の養殖をやっていましたのでもともと漁業はないのです。だからあげられたのです。いっそのこと、そのようにあがっているところを特区にしてみるのは、どうでしょうか。そういうところで、規制撤廃していくことより、世の中を少しづつ変えていくことが出来るのではないでしょうか。
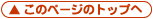
|